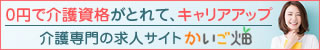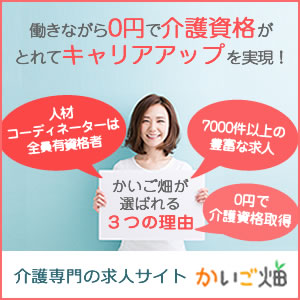介護職員初任者研修をスタートさせると、さまざまな「介護用語」を覚えることになります。
介護用語は専門性が高いため新しい用語も多く、最初は戸惑うことも多いかもしれませんね。
特に研修中は要介護者に対する尊厳の学びなども多いため「ノーマライゼーション」という言葉をよく聞きます。
これは初任者研修の試験問題の課題などにもよく出題されるキーワードですから、よく注意しておきましょう。
そこで今回はこの「ノーマライゼーションとは何か」について解説していきたいと思います。
ノーマライゼーションとはどのような原理か
初任者研修の試験問題にも出てくるノーマライゼーション。
育ての親といわれるベンクト・ニィリエ氏が定義したこの教えは私たちが生きる上で、とくに高齢者や障がいを持つ人にとって大切な事を教えています。
簡単に行ってしまうと介護者や障がい者であっても(ノーマル)な生活ができるよう、保証される環境整備を目指したものです。
またこの教えは「ノーマライゼーション8つの原理」という定義で成り立っており、世界的にも非常に評価が高いものとなっています。
さっそく一つずつ見ていきましょう。
Ⅰ.1日の正常なリズムを大切にする
ノーマライゼーションとは、たとえ重度の身体障がい者であっても、ベッドから出て服を着る日常を保てることを推奨しています。
これは要介護者のような方の場合、もし介護施設にいたとしても個人の時間に対する必要性を考慮しなければならず、時折グループのルーチンワークから離れることを意味します。
Ⅱ .日常の生活を大切にする
ほとんどの場合、人は一つの場所に暮らしながら会社に通ったり学校へ行くなどの活動を行います。
これは要支援者であっても同じ事です。
たとえ生活困難者であったとしても、幅広い経験と適切な社会的訓練により、社会の通常の時間を他の人と同じように過ごすことを目指します。
Ⅲ .休日や家族の時間を大切にする
ノーマライゼーションとは、1年における通常の休憩(リズム)を体験することも指します。例えば長期旅行などが該当します。
どんな人でも年に一度は長期旅行をし、生活状況を整えリフレッシュを図ることが大切です。
Ⅳ ライフサイクルを行った場所に暮らす
老後になると、時に人は住み慣れた場所を離れて老後施設などに移り住む事を余儀なくされます。
ただし、老後になればなるほど、慣れ親しんだ環境や知人との接触が大切となってくるため、例え老人ホームなどへ移り住む場合にも、地元の地域からあまり離れていない場所であることが大切となってきます。
Ⅴ 個人としての尊厳と自己決定権
ノーマライゼーションにおいては、生活困難者であっても可能な限り個人としての尊厳を守られなければなりません。
1968年にスェーデンの8つの都市で開催された会議において、18歳から30歳までの若い生活困難者は、子どもたちと一緒の活動に参加することや、大きい施設などに入ることに反対の意思を示しました。
彼らは普通の人と同じように自由や希望を持って生きています。ですから周囲もそれを認め、尊重することが大切だと伝えています。
Ⅵ 異性との良い関係を築く
ノーマライゼーションでは、子どもでも大人でも異性との良い関係を育めることを目指します。
さらに思春期には異性との関わりに興味を持ち、大人になってからの恋愛や結婚なども推奨しています。
Ⅶ 基本的な公的財産援助
ノーマライゼーションでは誰もが公的な援助を受けられるとされています。
その援助とは、それぞれの国が定める児童手当、個人年金、老年手当、または最低賃金が含まれます。
Ⅷ 普通の地域で暮らし、普通の家に住む
これは障がい者だからといって孤立するような大きな施設に入ることは常識ではない、という事を示唆しています。
他の人と同じような場所に住み、通常のような家に暮らすことで、地域の人たちのなかでもうまく馴染むことは十分可能です。
介護職員初任者研修を受講できるスクール一覧
| 【北海道・東北エリア】 |
| 北海道 |
| 【関東エリア】 |
| 東京23区|東京23区外|神奈川|千葉|埼玉|茨城|栃木|群馬 |
| 【甲信越・北陸エリア】 |
| 山梨 |
| 【東海エリア】 |
| 愛知 |
| 【近畿エリア】 |
| 大阪 |
| 【中国エリア】 |
| 島根 |
| 【四国エリア】 |
| 香川 |
| 【九州・沖縄エリア】 |
| 福岡 |
介護職員初任者研修にもよく出てくる
ノーマライゼーションの考え方は、質の高い介護業務をする上では欠かせない考え方です。
この原理を知ることでより良い介護サポートが目指せます。
また研修のレポートに、このノーマライゼーションに関する記述を求められる場合があります。
8つの原理をすべて把握するのは難しいので、要点だけでも押さえておくといいでしょう。
QOLなどの用語とともに、チェックしておくことが大切です。
他の用語集もいくつかありますので、ぜひ用語辞典などを有効活用してくださいね!