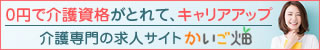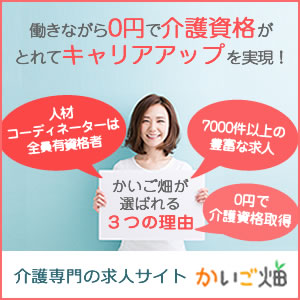食事をすることは私たち人間にとって、生きる楽しみであり生命を維持する上でも大切なこと。要介護者にとっても同じですね。
しかし、ヘルパーの立場からすると要介護の方が食事をしているときは注意をしなくてはいけません。
なぜなら、嚥下機能(えんげきのう)が衰えてしまっているからです。
このような要介護者が食事をとる場合、時折むせて苦しい思いをしなくてはいけなくなってしまいます。最悪の場合は、死に至る可能性もあるのです。
今回は介護士がお食事の手伝いをする上で知っておき、嚥下機能についてどのようなケアが必要かをご紹介します。
嚥下(えんげ)とは食べ物を消化するまでの流れ
まず嚥下について考えてみましょう。
嚥下は目の前にある食べ物をまず認知し、次に口や喉などを通じて胃に行くまでのすべてのことを指します。
嚥下については簡単に分けると5つのパターンに分かれます。
①認知期(先行期)
食べ物を見たり臭いを嗅いだりして「食べ物だ!」ということを脳が理解します。この時に一口の大きさを決めたり、どのように食べるのかを決めます。この時、正常ならば唾液が出てきます。食べ物を見た時によだれが出てくるのはこの認知期です。
②咀嚼期(準備期)
食べ物を咀嚼(そしゃく)して飲み込みやすい大きさにします。この時、唾液と食べ物が混ざりさらに飲み込みやすくなります。この時できた飲み込む前の段階のものを食塊(しょっかい)と呼びます。
③口腔期
舌を動かして、食塊を飲み込む準備をします。食塊を喉の奥へ移動させるのです。
④咽頭期
食道へ送り込む段階です。
・食塊が鼻へ逆流しないように、軟口蓋と呼ばれる部分で鼻と口の間を閉じます。
・のどが上がって声を出す声門と呼ばれる部分を閉鎖します。
・気管に入らないように気管の入り口を閉鎖します
⑤食道期
食塊を胃に送る段階です。腸が伸びたり縮んだりを何度も繰り返して胃まで運ぶ段階です。ここでは体が勝手に行う自発運動になります。
高齢者の嚥下機能は衰えている
![]()
私たちが介護させていただく、高齢者の嚥下機能についても知っておきましょう。
高齢の方は私たちと違って、食べ物を飲み込む機能が衰えてしまっています。
その機能は主に次の3つです。
・器質的原因
口の中から胃までの器官に問題がある状態です。
口に入れたものがが胃まで行けなくなる、という構造の問題があります。
その結果うまく飲み込めナックなった状況です。
先天的な病気でそうなることもありますが、高齢者の場合は病気などでそうなることのほうが多いです。
・機能的原因
体の異状が見られることはなく、神経や筋肉に問題が起こるパターンです。
脳の病気や、パーキンソン病などが原因で神経と筋肉に嚥下機能が衰えている可能性があります。
他にも薬の副作用でそうなってしまうことがあります。
加えて、加齢によって飲み込むのに必要な筋力が弱くなってしまっているのも理由の1つになります。
そのせいで、食道へ流れるはずの食塊が気管にながれこんでしまいます。
・心理的原因
最後は心的原因です。嫌なことがあったり、うつ病であったりしてメンタルの面から嚥下の障害が起こることがあり得ます。
これらの原因から嚥下障害を起こしやすい状況と言われています。
そうなってしまうと食事から栄養や水分が取れなくなったり、のどに詰まって窒息してしまう可能性もあります。
嚥下障害になっている状態です。嚥性肺炎という気管に食塊が入って、肺炎になってしまう可能性があるのです。
そうならないためにも、ヘルパーなどの介護士をはじめ、家族が見ていきたいポイントをまとめてみました。
1.食事中にむせなどはないか?
高齢者が特にむせやすいのは水分です。
味噌汁やお水などの水分や、水分と他のものが入った食べ物です。
また、自分の唾液でむせる場合もあるのでチェックしていきましょう。
ちなみに、水分を取ってむせてしまうと嫌だからと飲まない方もいます。脱水になる可能性もあるので、トロミを付けるなどして対策をするといいです。
2.やわらかいものをばかりを食べていないか?
固いものを食べるには大量の唾液とたくさん噛む必要があります。
その結果、食べやすいものを好むことがよく見られます。
特におかゆや麺類などが食べやすいので、それらのものを好んで食べるようになるのです。
3.食後に声がおかしくないか?
食事をした後は、声がすこし枯れた状態になるのも注意が必要です。
口の中に食べ物が飲み込めず、残ったままの状態になることから痰が絡んで声がかれてしまいます。
こういった点を見つけたら、あなたがケアをしている要介護者のそれからの食事に関しても気を付けてあげられますから、ぜひ目安としてください。
最後に
介護職として勤務しているなら知っておきたい嚥下の仕組みをまとめてみました。
嚥下はさまざまな原因があり、高齢者の嚥下機能は低下しています。
利用者さまに苦しい思いをさせないためにも、これらのことを頭に入れて介護をすると、より良い介護ができるようになれるでしょう。