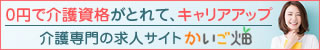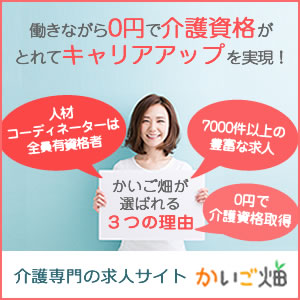「介護施設の夜勤は辛い」ということは、これから介護職をはじめるあなたも想像できると思います。
忙しい場合、仮眠や休憩が取れないことも珍しくありません。
公益財団法人介護労働安定センターの調査によりますと、深夜勤務の有無について尋ねたところ「ない」と答えた人はが72パーセント。「ある」と答えた人が25.8パーセントでした。
また深夜勤務を「ある」と回答した方へ深夜勤務の回数を尋ねたところ最も高かったのが「5回以上7回未満」という結果で39パーセントに近い回答があったそうです。
また夜間は職員の数が少ないので、ひとりで何人もの利用者を見るワンオペをしなければならない時間帯が時として発生します。
もしあなたがはじめて「ワンオペ」を経験した場合、いったいどのような事がおこるのでしょうか。
ここでは介護施設に見られるワンオペ夜勤の実態と、ワンオペ夜勤が発生した場合の心がけを解説します。
ワンオペとは一人体制で業務を担う作業
すでにご存じかと思いますが、ワンオペとは「ワンオペレーション」の略で、ひとり体制で業務を行うことです。
これが夜勤の場合、ひとり体制の夜勤になりますから介護職員に大きな負担をかけます。
ほとんどの場合、日中は10名程度の利用者を一人で担当しますが、夜間は人数が減るため20名程度を一人で見ることになります。
夜間は利用者が寝ているため職員が少なくても問題ない、という考え方が根本にあるためです。
ですが、夜勤は思った以上に色々な問題が発生します。主には以下のような内容です。
- 昼夜逆転している利用者の対応
- 起床時刻の早い利用者の対応
- おむつ対応の利用者の排せつ介助
看護師不在の中で緊急時の対応も行わなければいけません。
深夜は利用者の動きが少ない時間が多いことも事実です。
しかし明け方の短時間に、重労働の業務が詰まっていることを考えると、日中の勤務よりもワンオペでの夜勤の方がたいへんだと言えます。
ワンオペ夜勤は小規模の施設などで起こりやすい
ワンオペ夜勤が実際おこる施設ですが、小規模の施設や、ユニット型の施設で発生しやすい傾向にあります。
なぜなら夜勤者ひとりが見られる利用者の数は、25名までと法律で定められているからです。
具体的な施設は以下の通りになります。
- グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護
- 一部の特別養護老人ホームや介護老人保健施設など
グループホームや小規模多機能型居宅介護の入居、宿泊利用者の定員は9名となっています。
小規模な特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、定員が20名前後です。
利用者の定員人数が、ワンオペ夜勤が行われる施設の目安となります。
また、100名規模の大きな施設であっても、ユニット型の施設は20名程度の利用者を、ひとりで見る場合もあります。
施設内に複数の夜勤者はいますが、協力して勤務することが難しいです。
ですからこういったケースも実質ワンオペ夜勤と言えるでしょう。
ワンオペ夜勤を行うために心がけることとは?
このようなワンオペ夜勤に潰されないために心がけるポイントですが、3つあります。
- 夜勤中に自主的な息抜きをする
- 事前に緊急時の対応を確認する
- 夜勤前後は体内時計を意識して過ごす
ひとつずつ順番に解説します。
1.自主的な息抜きをする
夜勤勤務のほとんどは休憩時間が定まっていない状態です。
ですので業務の合間を縫って、自分から積極的に休憩を行いましょう。
夜勤は普段できない事務作業や、優先順位の低い作業の時間に当ててしまいがちです。
ですが、疲労は確実に溜まっていくので、10分でも良いのでリラックスできる時間を設けると良いでしょう。
少しリフレッシュするだけで明け方から翌日にかけての疲労や、仕事のパフォーマンスが変わってきます。
- 足を延ばしてリラックスできる姿勢を取る
- しばらく目をつぶる
- 仕事のことを考えないようにする
動かなければいけない時間以外はすべて休憩でも良いくらいです。
夜勤中は積極的に休みましょう。
2.事前に緊急時の対応を確認する
夜勤者の大きなストレスのひとつが、緊急時の対応です。
慌ててしまったりどうすれば良いかわからなくなってしまったりすることで、適切な対応を行うことが難しくなります。
いきなりの緊急事態であっても事前に対応を確認しておくことによりスムーズに動くことができます。
具体的には以下の3つです。
- 事故が起こりそうな利用者と、考えられる事故の内容と対策
- 体調面で注意が必要な利用者と、考えられる急変の内容と対策
- 日中の様子が普段と違う利用者と、どのように違っているかの把握
勤務開始時に緊急時の対応を想定しておくだけで、不測の事態にもある程度対応することができますから、ぜひ準備しておくといいでしょう。
3.夜勤前後は体内時計を意識して過ごす
夜勤中の疲労は夜勤前後の過ごし方で、夜勤中や夜勤後の疲労感は大きく変わります。
ポイントは体内時計がなるべく崩れないようにすることです。
夜勤当日と夜勤後の日中は少し仮眠を取り、夜勤前後の夜は本格的な睡眠を取るように意識すると良いでしょう。
具体的には以下の5点があります。
- 夜勤前日の夜は遅くならないうちに寝る(日付が変わる前)
- 夜勤当日の朝は普通に起きて、午前中は軽く活動する
- 夜勤当日の午後は1時間から3時間程度の昼寝をする
- 夜勤明けの日中は消化の良いものを食べて、3時間程度の昼寝をする
- 夜勤明けの夜はしっかりと睡眠を取る
夜勤前日の夜に徹夜したり、夜勤当日の日中に寝だめしたりすると夜勤中に睡魔が襲ってくる原因となります。
できるだけ体内時計を崩さないようにしましょう。
≫参考:医療法人社団 平成医会 サーカディアンリズムと私たちの生活
おわりに
現在介護職は人手不足が続いています。
そしてデータからみても、夜勤は業務の重大なミスを招きやすいとい事が懸念されています。
あなた自身の健康も考え、ワンオペになるほど忙しい施設は避けるに越したことはありませんね。
日本医労連によりますと、医療や介護現場の労働者の夜勤規制を進めるには、1日8時間以内で、勤務間隔12時間以上。さらに週32時間以内を目標とする労働時間改善を訴えています。
夜勤を行う場合には、あなた自身のワークライフバランスを十分に実現しながら2交代制を維持するだけの人材確保ができる施設の就職をまずは目指しましょう。
一つの小さなミスが利用者の命に関わる事態を招く可能性もあるのが介護職です。
どうしてもワンオペをせさるを得ない場合には、上記の内容を参考にしっかりと準備対策をおこなってみてください。
https://goodqualificationcare.com/6635-2/