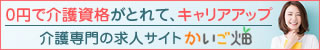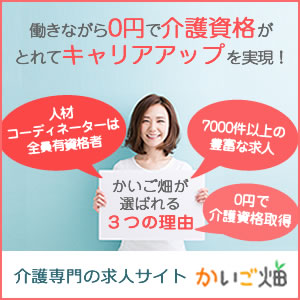今回、お話しするのは「介護職員初任者研修の問題や難易度」についてです。
あなたもご存じのとおり、介護職員初任者研修とは以前の「ヘルパー2級」に相当するものです。
ですが、実際にはどのような問題がでるのかや、難易度について不安な点もありますよね。
そこで、ここでは初任者研修の最終試験にでる問題について体験談をもとにご紹介していきます。
初任者研修の問題は厚生労働省や各所轄官庁が決めている
改めて介護職員初任者研修は、介護の仕事を始める人が基本的な知識と技術を学ぶことができます。
さらに頭で考えて覚えるための「講義」と身体を使って覚えるための「演習」があります。
介護職員初任者研修を受講するスクールは全国各地にあるので、近くのスクールで申し込むこめ、講義と演習を合わせると130時間分。すべてスクールで行ってくれます。
そしてすべての講義・演習を終えると「修了試験」と呼ばれるテストがありこちらのテストに合格することで晴れて介護職員初任者研修を修了することができます。
このテストは、内容を厚生労働省や各所轄官庁によって定められています。
つまり、スクールごとに大きな差や違いがある訳ではなく大まかな項目は決まっているということです。
介護職員初任者研修のテスト範囲や内容について
それでは、介護職員初任者研修のテスト内容について説明していきましょう。
まず、試験の範囲ですが130時間の講義・演習の中から出題されます。
テストは選択式と記述式の問題がありスクールにもよりますが基本的には選択式の問題が多いです。
記述式の問題はあっても数問になります。
これは、テストの時間が1時間と決まっているため、あまり多く記述式を作れないことが理由となっています。
試験問題はスクールによって違いますが、先ほども述べた通り厚生労働省や各所轄官庁で評価の基準が定められているので、大きく違うことはありません。
また、このテストは「落とすための試験」ではなく「学習内容を理解しているのか」を確認するための試験です。
なのでスクールの講義中に出やすいポイントや内容を教えてくれますし、講義にきちんと出席することがテストの対策の1つであると言えます。
合格率や難易度はどれくらいなのか?
試験の合格率はずばり90%を超えています。
このことからも「落とすための試験」ではないことがわかりますね。
難易度はあまり高くないですし講義や演習にしっかりと臨んで復習をすることで合格できます。
実際の内容ですが、全32問以上を選択式・記述式で出題し70点以上で合格ラインです。
具体的な試験内容についてみていきましょう。
1.職務の理解
サービスや現場に関する概念的なものを学ぶ分野で、2科目出題。
2.介護における尊厳の保持・自立支援・・・2科目出題。
3.介護の基本・・・介護の役割、安全確保など4科目が出題されます。
4.介護・福祉サービスの理解と医療との連携・・・3科目出題されます。
5.介護におけるコミュニケーション技術・・・2科目出題。
6.老化の理解・・・高齢者の心身の変化について2科目出題。
7.認知症の理解で4科目出題されます。
8.障害の理解・・障害に関する知識や利用者家族の心理など3科目。
9.こころとからだのしくみと生活支援技術・・・12科目出題されます。
テストは選択式が大半を占めるので、日ごろから予習・復習が重要です。
合格するための平均点は70点以上になってはいますが、一つひとつの問題に引っ掛け問題が1つあるくらいなので、問題文を丁寧に読んでから取りかかればミスをすることもありません。
また万が一、試験に落ちてしまったとしても、ほとんどのスクールにおいて、追試験・再試験を行っているので安心して試験に取りかかれます。
介護職員初任者研修の資格取得は難しい?合格率・難易度について
初任者研修における実技試験の主な内容とは?
次に実技試験についてです。
介護職員初任者研修の実技試験を行っているスクールはあまり多くありません。
ですが、これから介護の仕事をする方には必要なスキル・知識になることは間違いないです。
実技試験があることでより介護について学ぶことができると思いますよ。
- 衣類の着脱介助
- 歩行介助・移乗介助
- 排泄介助
- ベッドメイキング・体位交換
- 食事介助・口腔ケア
一つずつ見ていきましょう。
これは「着せたり脱がせたりするものです。」
片方の腕や足に麻痺がある利用者をイメージした着替えなどになります。
②の歩行介助は杖歩行の利用者や車イスの利用者の歩行介助を行います。
利用者のどちら側に立つのか、足に麻痺があるのかを確認することが必要です。
移乗介助は
車イス→ベッド
ベッド→車イス
のように利用者が移乗する時に介助するものです。
立ち上がりが不安定なのか、どちら側に麻痺があるのかを確認することが大切です。
③の排泄介助は利用者の排泄をサポートし、介助により交換することです。
利用者のプライバシーを尊重すること(カーテンや臭いなど)、協力動作がある場合は協力してもらうことが大切です。
④のベッドメイキングはシーツ交換におけるポイントを抑えることが大切です。
三角折りができているのか、シーツがピンと張っているかを確認することが必要です。
体位交換は利用者に褥瘡(皮膚が身体の圧力で破ける)を防ぐために行うもので、除圧がしっかりできているかの確認が大切です。
https://goodqualificationcare.com/group-home-jobs/
⑤の食事介助は利用者が食事をスムーズに食べるように行うことが必要です。
口腔ケアは利用者の口腔内を清潔にするために行うことが必要で入れ歯なのか、うがいができるのかなどを確認することが大切です。
テスト勉強〜試験当日までの流れについて
いよいよテスト勉強〜試験当日までの流れを説明します。
テスト勉強で大切なのは、講義中に講師から「ここは重要です」と言われるポイントを抑えておくことです。
ここは重要です=テストに出る可能性がかなり高いと思ってもらって構いません。
言われたポイントを重点的に復習しましょう。
また、レポートや課題の中から文言を少し変えたような問題も出題されやすいです。
内容と文章全体を理解しておくことも重要になります。
またテスト当日ですが「1つの問題にこだわりすぎない」ことです。なぜなら、テストは1時間と短い時間の中で行うから。
「とりあえず解ける問題から解いて残りの問題は戻って考える」とした方が焦らずに済みますよ。
体験談をふまえた初任者研修(ポイント)
ここからは体験談です。
まずは、初任者研修の講義はかなり「長い」です。
朝から夕方まで(昼休憩はあります)ずっと座学で睡魔に襲われることはしょっちゅうです。
講師の方が「ここポイントだよ」と言った時に寝てしまっていたら聞き取れませんね。
スクールは何人かの人と受けるので協力しておけば、ポイントを聞き逃してもお互いに助け合うことができるかもしれません。
私も聞き逃したりした時に教えてもらったり、教えたりと助け合ってなんとかなりました(笑)
教科書をスラスラと読む講師の方もいらっしゃるので、持ち物としてカラーペンは必須です。
ポイントもスラスラと読む場合はノートに写す暇がないと困りますよね。
そこで色ペンで線を引くと後からの復習に役立ちます。
ちなみに、筆者の受けたテストは4択の選択式でした。
明らかに違う選択肢が1つはあるので、焦らずに消していくことがコツです。
実技試験の場合は「声かけ」がとても大切です。
声かけは、利用者役の人に伝えるためでもありますが、自分の動作を確認しながらできるのではっきりと言いながら実技を行うことで、緊張していてもミスをカバーしやすくなります。
まとめ
今回は介護職員初任者研修における、実際のテストについてご紹介しました。
介護職員初任者研修のテストのポイントは以下の通りです。
・講義をしっかりと受けてポイントを抑える。
・テストの問題は分かるところから解いていく。
・文章を丁寧に読んで、明らかに違う選択肢を先に消す。
・実技試験は「声かけ」で自分のミスをカバーする。
これらを行うことで合格しやすくなります。是非、参考にしてみてください。
\登録は2分♪一括取り寄せでじっくり比較♬/
まだフォームには行きません。お近くの資料請求トップへ